医療機器 保険適用支援
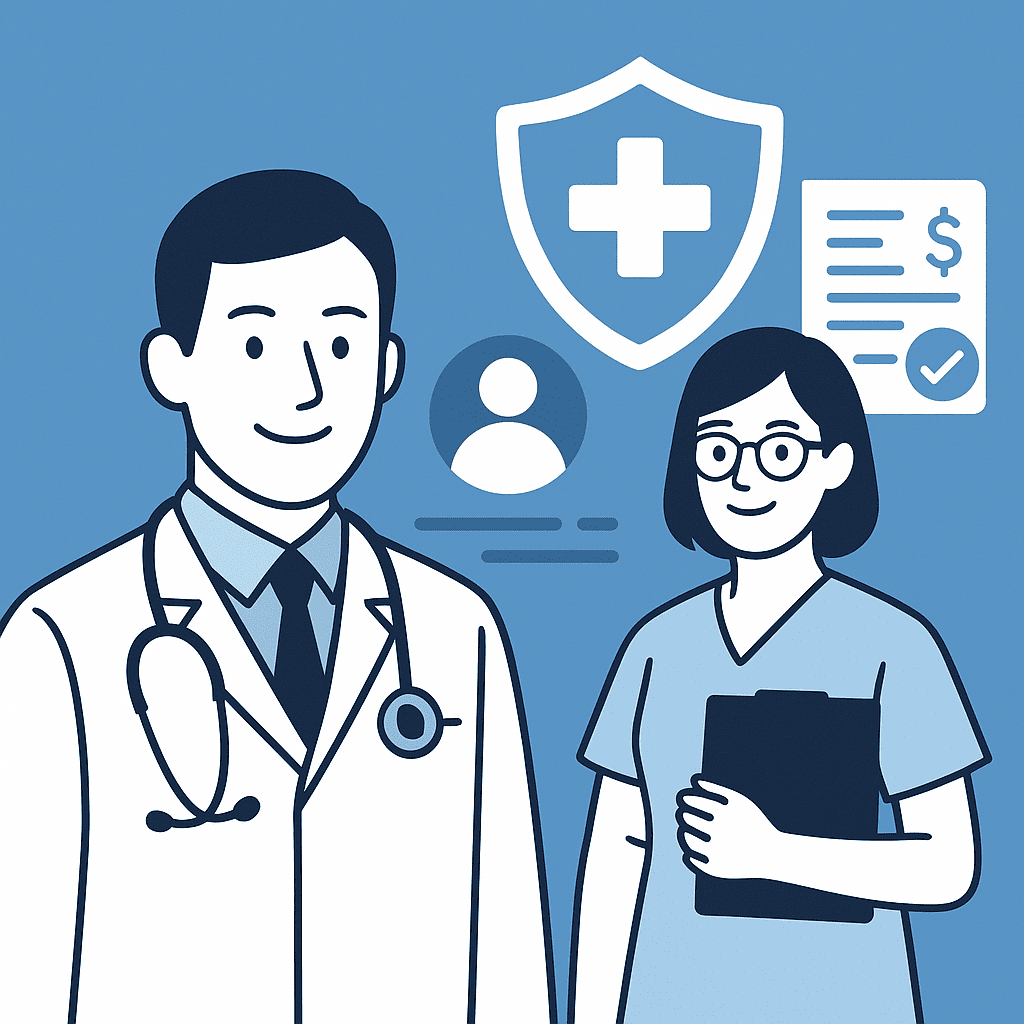
保険適用を見据えた SaMD(プログラム医療機器)・IVD(体外診断用医薬品)の開発支援
保険適用戦略の立案から行政・関連学会への実地対応までを一貫して支援します。
医療機器にとっての保険適用とは
医療機器ビジネスにおいて、新規保険適用の獲得は極めて重要な課題です。
しかしその過程は非常に見通しが立ちづらく、制度上の知識だけでは解決できない“不文律”が多く存在します。
この難関を乗り越えるには、保険制度の理解だけでなく、保険適用審査における暗黙のルールの理解、関係各所との連携経験が欠かせません。
弊社は2003年の設立以来、保険適用に特化した専業コンサルタントとして、数多くの医療機器の保険適用を実現してまいりました。
近年では SaMD(プログラム医療機器)への対応も多数手がけており、ニーズの高まりに応じた支援体制を整えています。まずは初回の無料相談をぜひご活用ください。
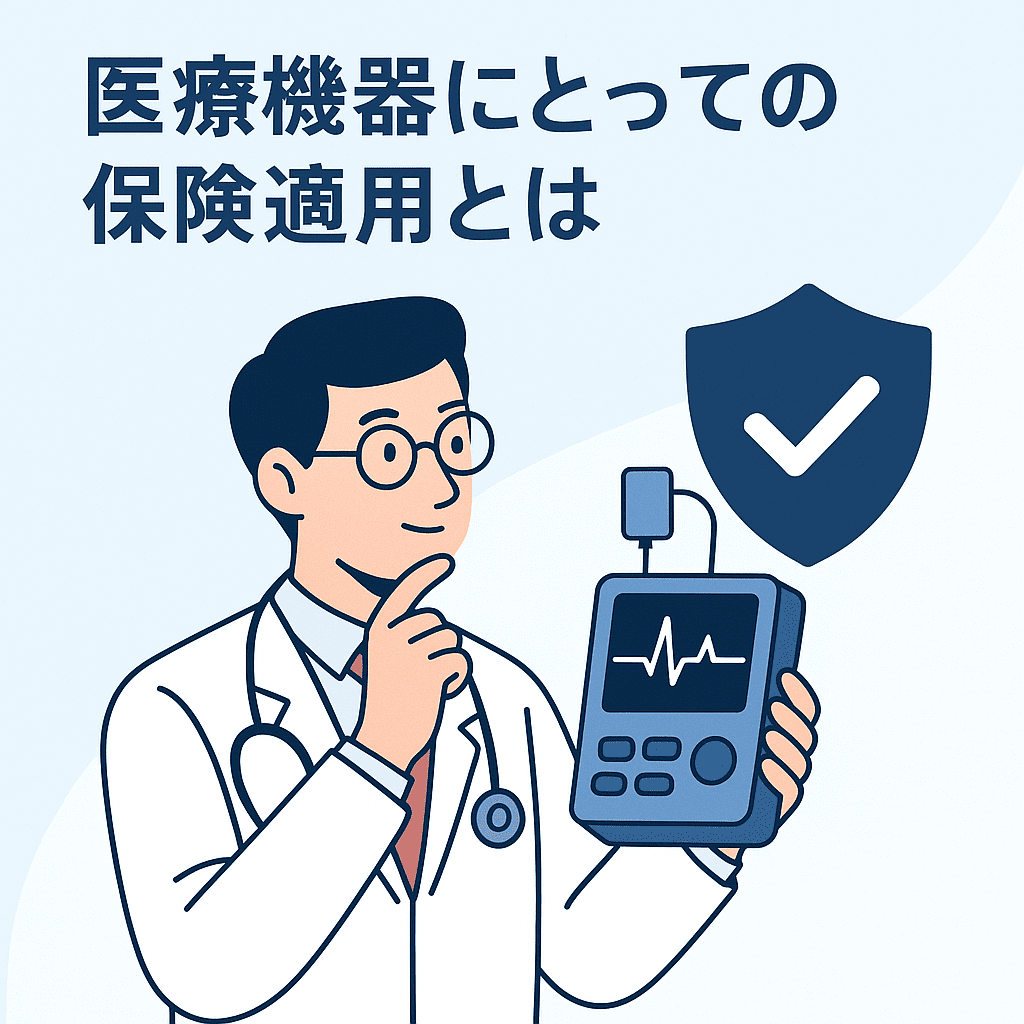
医療機器ビジネスと保険適用
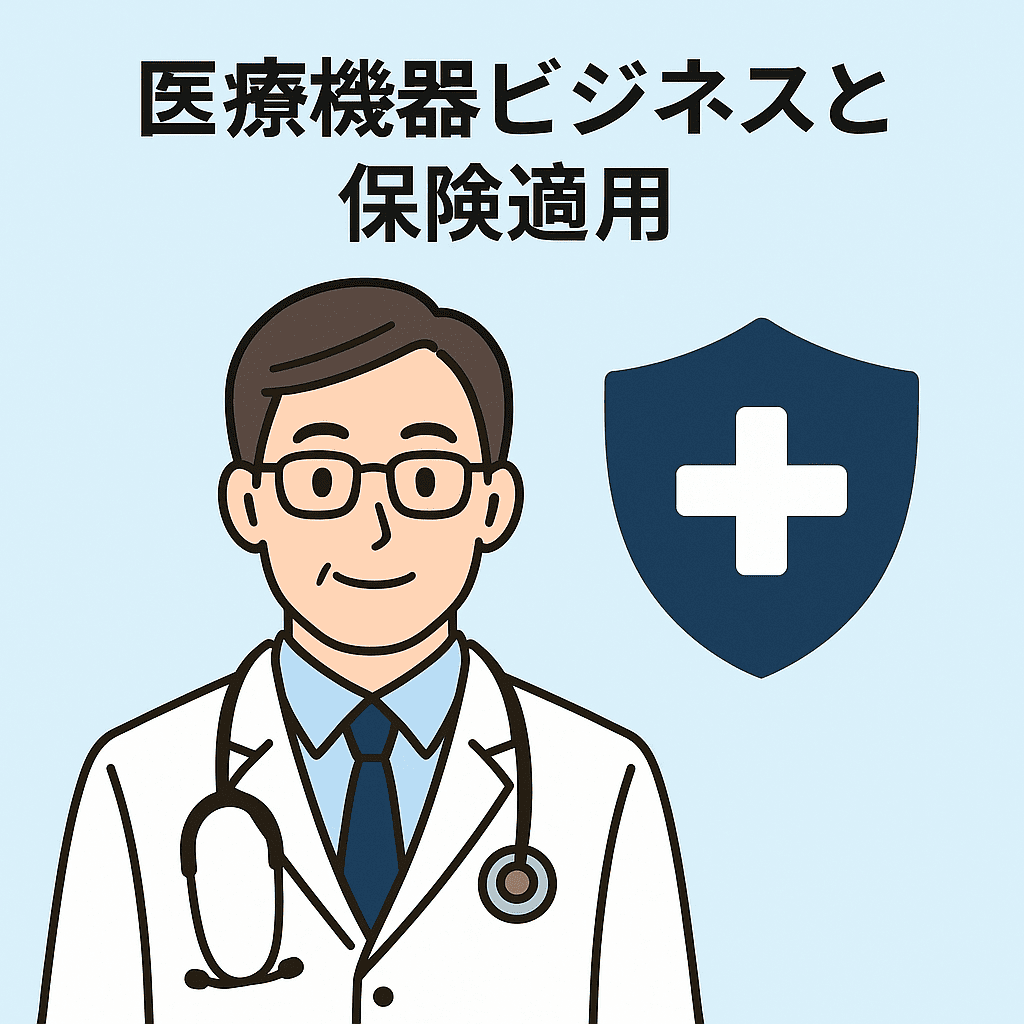
日本の医療保険制度は、国民に対し低コストかつ高品質な医療を提供する世界的にも優れた制度です。
その一方で、医療供給側(医療機関・医薬品・医療機器など)には厳しい査定・価格統制が行われています。
現在の制度では混合診療が実質的に認められておらず、医療機器が保険適用を受けない限り、臨床現場での普及は厳しいと言わざるを得ません。
出口戦略として、開発段階から「保険適用」を見据えることが不可欠です。
なぜ新規保険適用は難しいのか
SaMD や IVD を含む医療機器の新規保険適用に関しては、通知や手引き書だけでその全体像を把握することは困難です。
また、製品の価値を既存医療体系に照らし、その有用性があるかを立証する必要がありますがそれらに対する審査は極めて厳しいものです。
薬事承認が「製品自体の有効性・安全性」を審査するのに対し、保険適用では「医療経済的な有用性」が問われます。
一方保険適用申請では、患者・医師・病院・保険者それぞれの視点に立った「総合的な有益性」を、エビデンスで裏付ける必要があるのです。
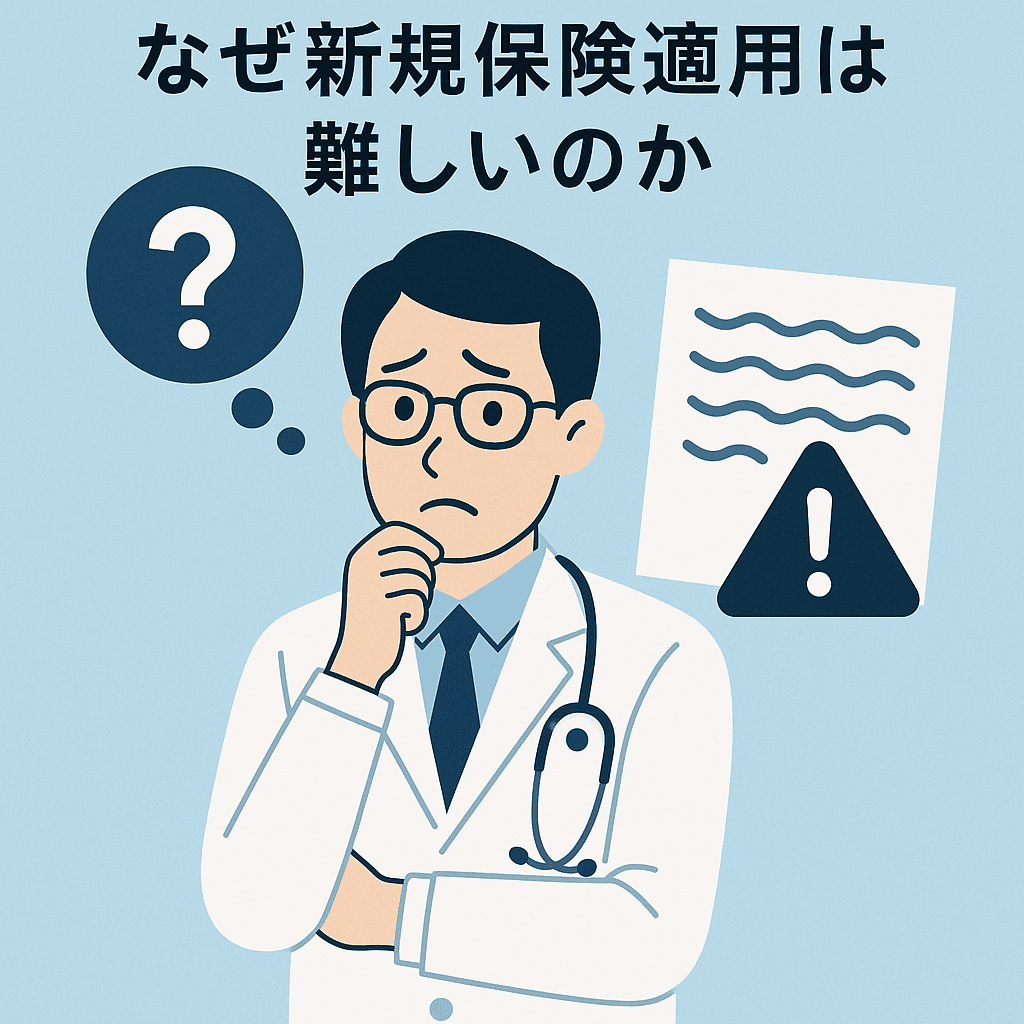
保険適用が製品価値を左右する
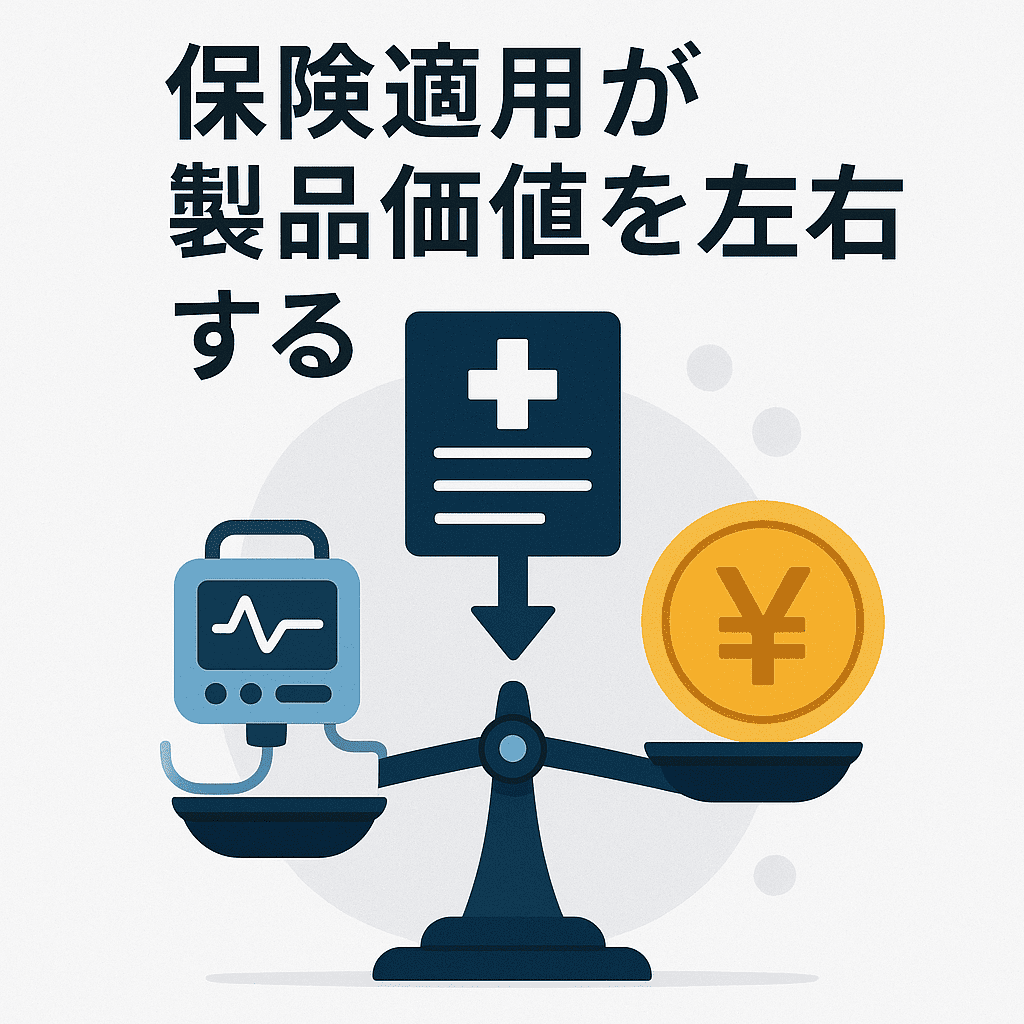
通常、製品の価格は需要と供給、売り手と買い手の感覚で決まりますが、保険適用においてはそうした要素は一切排除されます。
厚生労働省は、その製品が医療現場においてどのような臨床的価値をもたらすかを評価し、保険診療のバランスと予算を考慮して償還価格(保険点数)を決定します。
その際、審査の公平性を保つために医療機器事業者(製販業者)と審査側との直接折衝は制度的に禁止されています。
このため、全ては書面上で戦略的かつ論理的に主張する事が求められ、それなりのアイデアや工夫が重要です。
製品価値の訴求には戦略が必要
医療機器の臨床的有用性を正しく訴求することが、適切な保険適用を受ける第一歩です。
公益性の視点を持ち、患者・医療従事者・医療経済それぞれにとってのベネフィットを複数の角度から丁寧に立証することが求められます。
有用性とは、単に機器単体の性能ではなく、導入後に何がどの様に改善されるのかを定量的に比較検討し、根拠を示すことです。
これは申請プロセスの中でも最も難易度が高く、弊社が特に強みとする支援領域です。
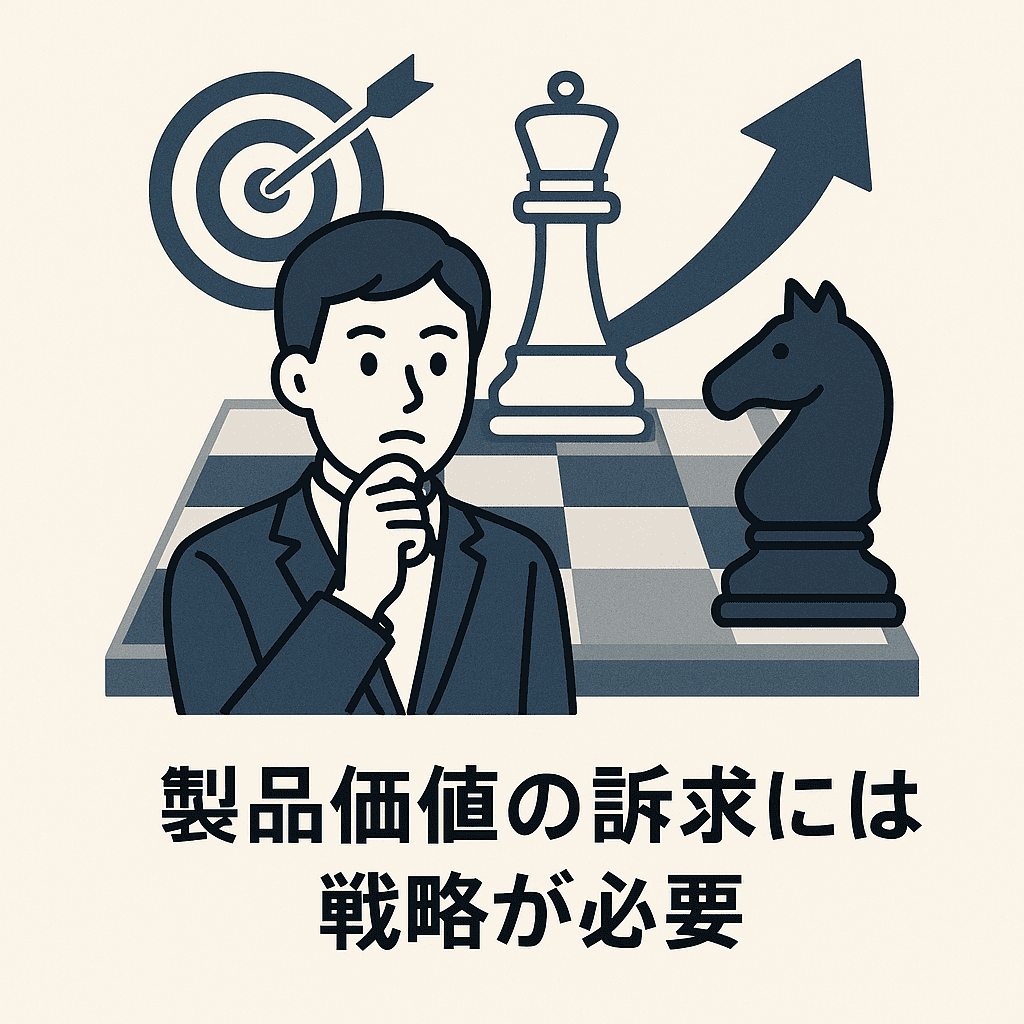
対象患者・算定要件・施設基準

保険適用の結果として設定されるのは、点数や償還価格だけではありません。対象患者の条件、施設基準、算定要件なども慎重に定義され、それが実際の販売に大きな影響を及ぼします。
特に、「誰に」「どのように」使われる医療機器なのかの説明が曖昧だと、点数の低評価や施設基準のハードルが高くなる可能性があります。
こうした周辺条件まで含めた対策を行うことが、実効性のある保険適用支援といえます。
関連学会との連携
近年では、保険適用の条件や適応範囲について「関連学会が定める基準」に準拠するケースが増えてきました。
これは厚労省が学会との連携を重視していることを意味します。
そのため、製販業者が関連学会に働きかけ、基準の策定や公表を促進することが必要不可欠です。
弊社では、学会関係者との調整や連携支援、場合によっては協働体制の構築まで支援実績があります。
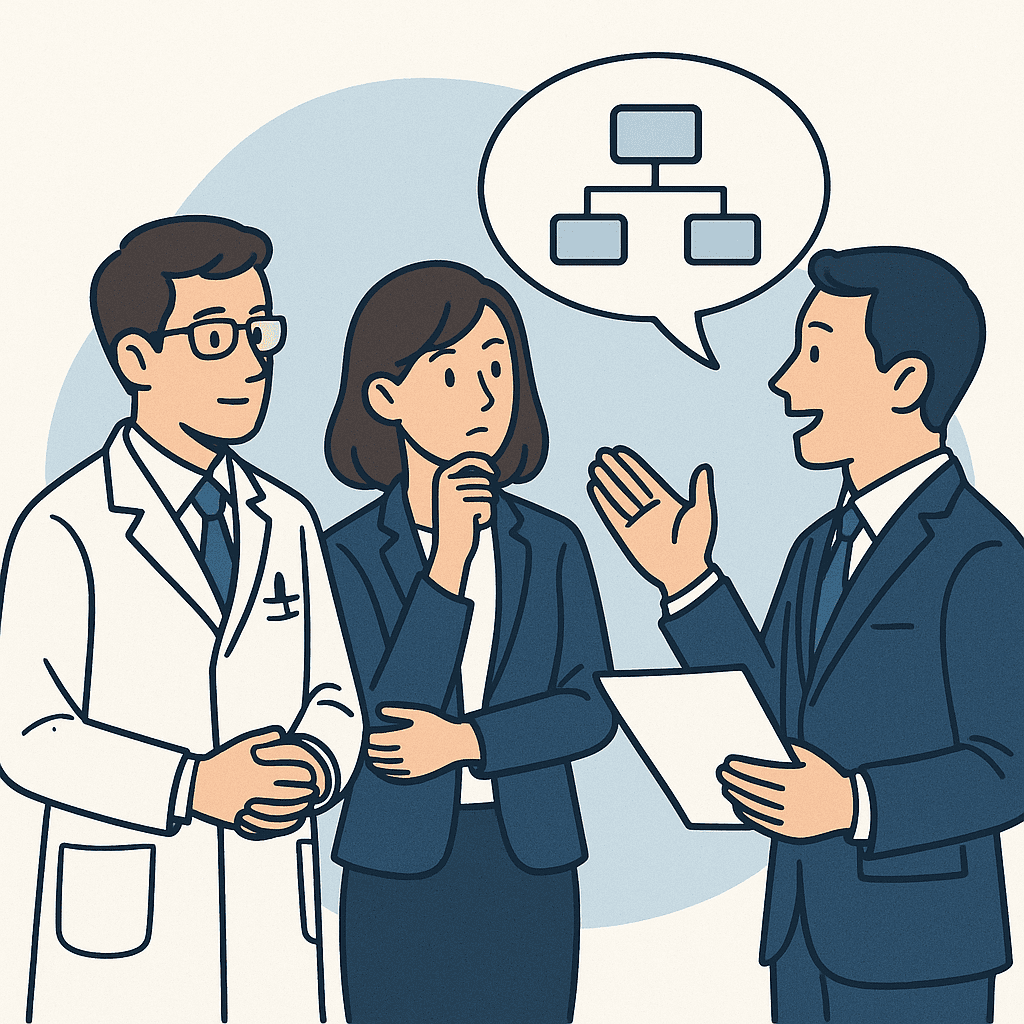
保険適用のルートと申請方法
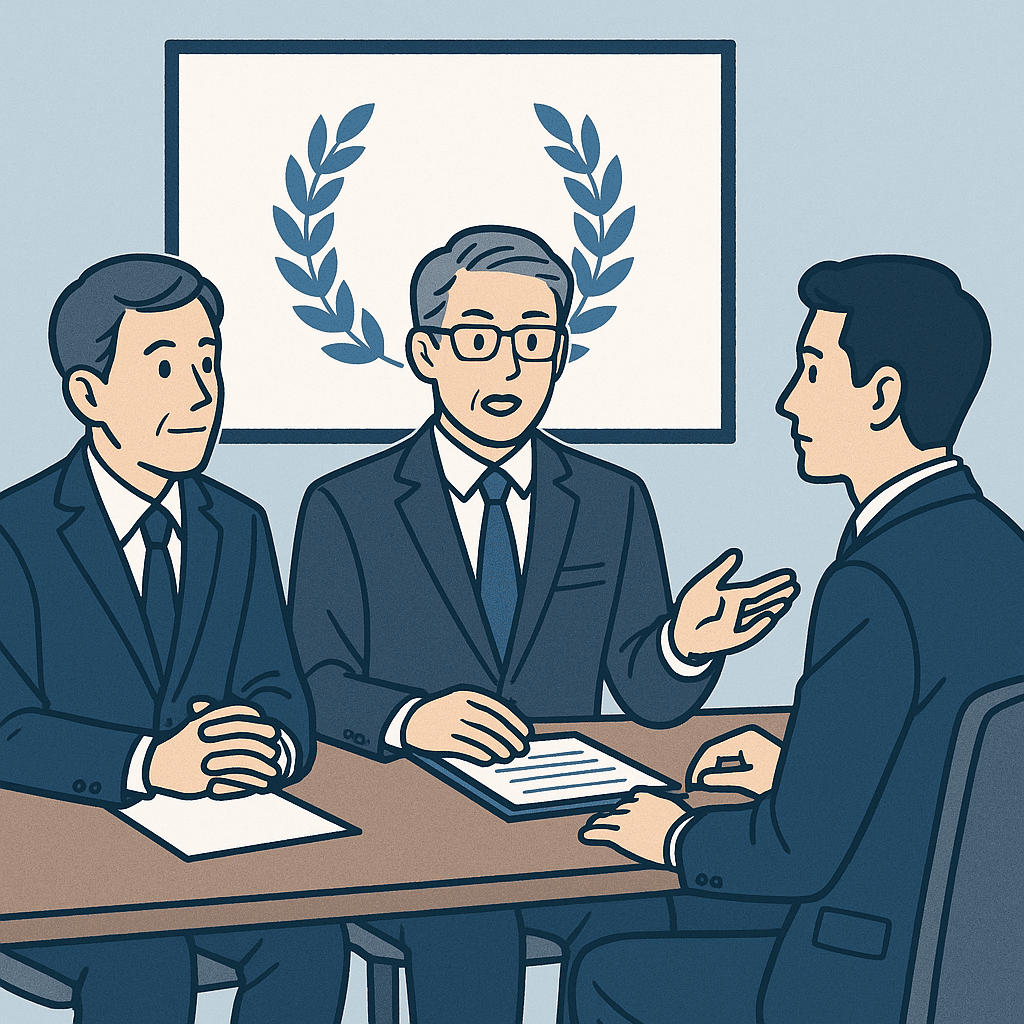
保険適用の申請には主に二つのルートがあります。
1.製品の承認保有者が提出する「保険適用希望書」による申請
2.関連学会が提出する「医療技術評価提案書」による診療報酬改定時の申請
それぞれの申請形式には独自のポイントがあり、どちらが適しているかは製品や市場戦略によって異なります。
弊社では、これらのルート選定から書類作成、審査官ヒアリング対応まで総合的に支援しています。
特に、「誰に」「どのように」使われる医療機器なのかの説明が曖昧だと、点数の低評価や施設基準のハードルが高くなる可能性があります。
こうした周辺条件まで含めた対策を行うことが、実効性のある保険適用支援といえます。
診療報酬改定と提案書作成の重要性
医療技術評価提案書は、関連学会が提出するものと思われがちですが、医療機器中心の技術に関しては製販業者主導で作成する方が望ましい場合が多くみられます。
とくに医療機器費用が点数構成比に占める割合が大きい場合は、業者側の情報とノウハウが不可欠です。
実際に、機器費用の説明が不十分だったため、保険点数が不適切に低く設定されてしまった事例がいくつかあります。
その増点のため弊社が依頼された事案は提案書作成とその後の多角的な支援により、約3倍の点数増加に成功した経験があります。
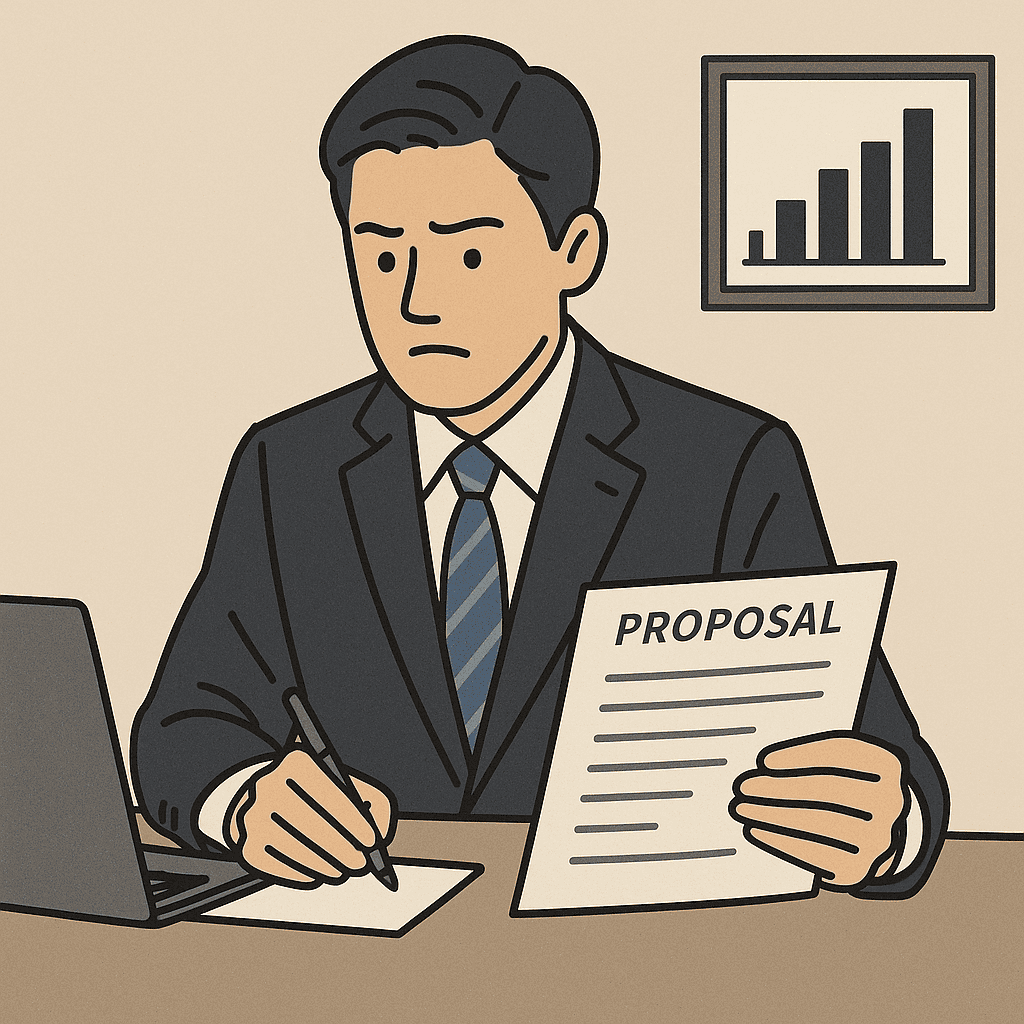
SaMD(プログラム医療機器)の特性と課題
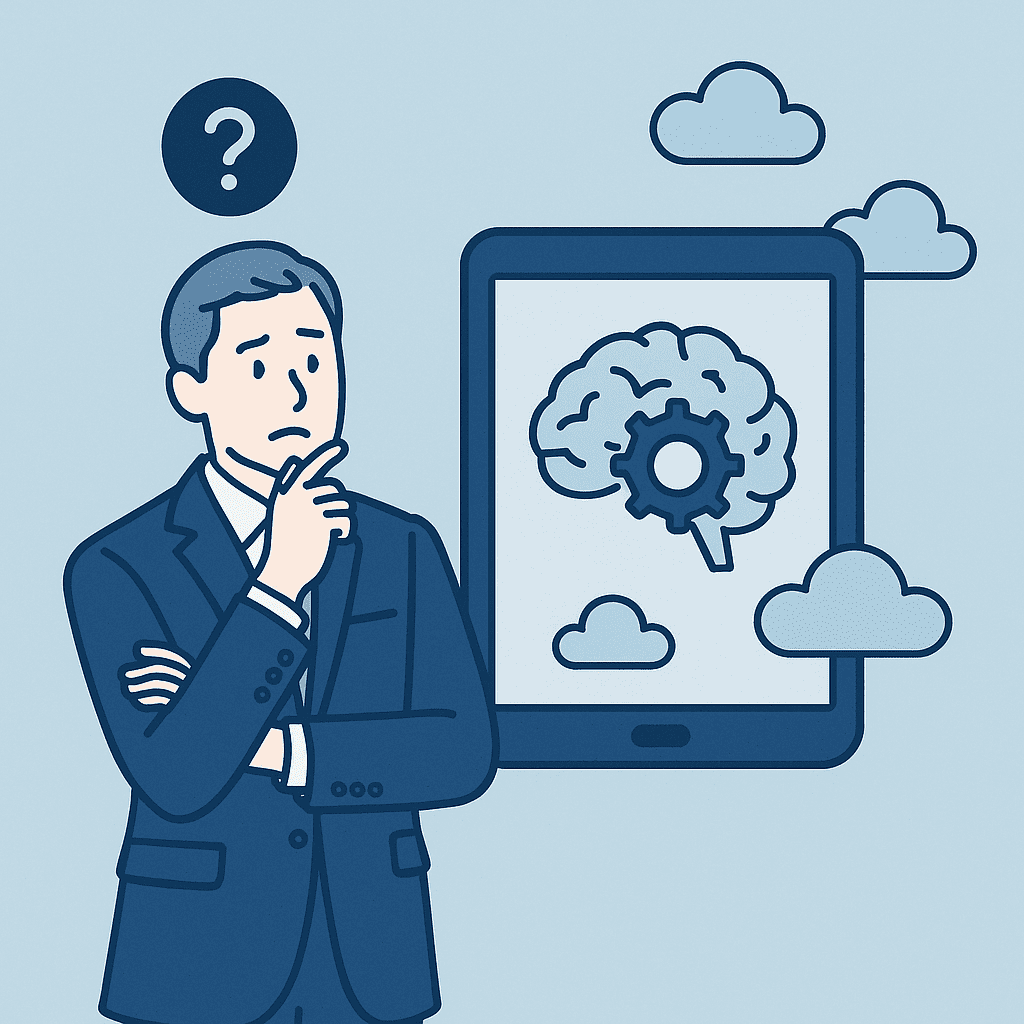
SaMD は急速に開発が進んでいますが、保険適用された事例はまだ少数です。その背景には、臨床現場との整合性、公益性の不足、審査委員の理解不足といった課題があります。
弊社が支援したあるSaMDの事例では、優れた技術であるにも関わらず、保険審査が求める臨床ニーズと乖離があり、仕様変更をアドバイスしました。
開発支援の段階で適切な方向修正ができれば、後工程でのリスクを大きく軽減できます。
企画・開発段階のSaMDに不安を感じている方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
価値観へのチャレンジと啓蒙活動
保険適用における審査は、行政だけでなく、KOL(分野の重鎮医師)による評価が大きな影響を与えるのが現実です。
しかし、新しい医療機器や技術に対して必ずしも理解が十分であるとは限りません。
こうした状況を打開するには、関連分野のKOLに対する戦略的な啓蒙活動=“広報的営業”が効果的です。弊社では、こうした情報発信・協力体制の構築にも力を入れております。
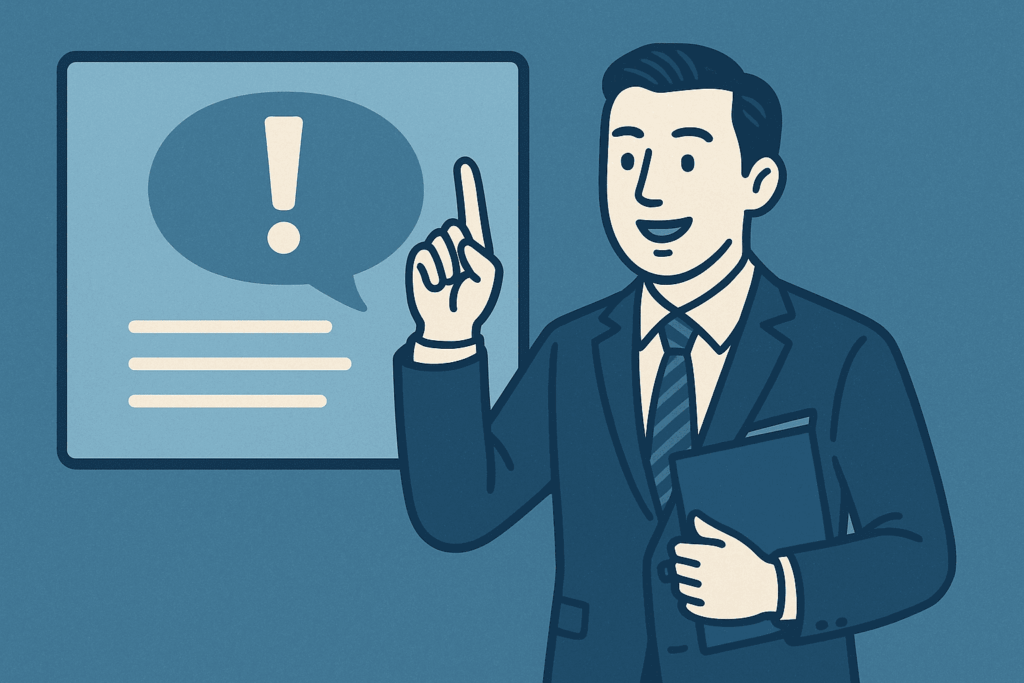
まとめ:保険適用を成功に導くために
医療機器の保険適用は、技術力だけでなく戦略と現場において可能な事全てを実行する
覚悟が必要ですの総合勝負です。
弊社は簡易な書類のレビューから始まりご依頼者の要望次第ではありますがそのチームの一員
として支援をして参ります。
初回相談は無料です
無料初回相談では必要に応じ守秘義務契約を締結の上、
保険適用に向けた大まかな製品評価と戦略、
見通しのほか様々なご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

